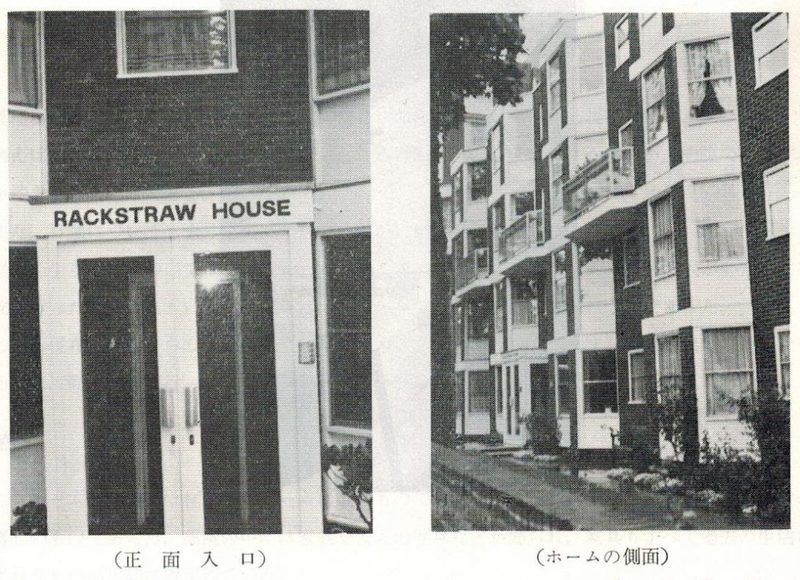2014.08.20
小野 鎭
小野先生の一期一会地球旅⑱「社会福祉施設処遇技術調査研究と研修事業」

一期一会 地球旅 18 「社会福祉施設処遇技術調査研究並びに研修事業」に添乗して その3 英国のこと
昭和47年度(1972年度)に始まった財団法人社会福祉調査会の「社会福祉施設処遇技術調査研究並びに研修事業」の報告書が十数冊ある。但し、事業名は途中から「民間社会福祉施設等職員海外研修調査事業」と名称が変わっている。また、主催団体そのものが財団法人社会福祉振興・試験センターと改組されており、いろいろなところに時代の流れの変化を感じる。前回書いたように筆者はこの研修事業の旅行業務を73年から担当させていただき、25年以上にわたって社としても旅行業務をご下命いただいてきた。この間に様々な福祉サービスの在り方そのものも変化してきたし、用語なども変わってきた。報告書を見るたびに添乗したその時々のことを思い出して感慨深いものがある。 最初のころは、欧州が多かったが、77年頃からは米国やカナダが多くなり、特に知的障害関係分野の施設処遇や地域ケア、研究などの大きな変化を感じてきたような気がする。このことは、次から書くことにして、今回は、75年の研修事業報告書にかかれていることの中からいくつかを上げてみたい。 冒頭の主催者あいさつにこの研修事業の目的が述べられている。 「昨今の我が国社会福祉施設の現状は、遅まきながらも年々施設の整備改善が行われ、一部には欧米諸国のそれらと比較しても何ら遜色のない完備したものも見受けられるに至ったことは、この途に携わる者として、真にご同慶に堪えない次第です。翻ってそれら施設の運営面、すなわち収容者に対する医療や保健衛生、とりわけ、生活指導や作業補導といった処遇技術の面、あるいは日常生活の上における介護技術の面となると遺憾ながら先進諸国のそれらには未だ相当の遅れのあることは否めない事実です。 こうした事情に鑑み、わが国社会福祉施設の今後における運営面の改善に貢献したいということで、欧州先進国における社会福祉施設の特に処遇技術等に関する理論と実践について実地に調査研究することを企画してきました。」とある。このような意図のもとでとらえられた一つの傾向としては、「いずれの施設に於いても、施設に収容するということは最終的な方法であって、特別な事情のもとにある者を除いては、極力、その者の家庭生活に重点を置いて処遇しようとする流れにあるということである。」と付されている。 この主催団体の序に対して、75年研修団の団長報告に次のようなくだりがある。一つは、出発時の